Webアクセシビリティ達成基準「1.3.2 意味のある順序の達成基準」の話
- Webアクセシビリティ
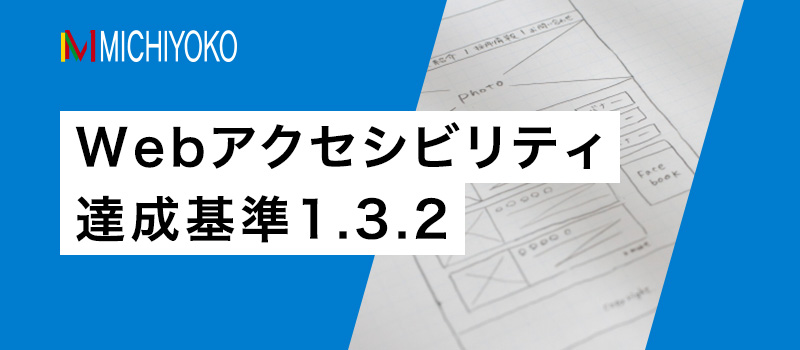
こんにちは、道洋行東京支店Web制作スタッフのT.Y.です。
前回はWebアクセシビリティ達成基準「1.3.1 情報及び関係性の達成基準」ついて解説しました。
続けて今回は「1.3.2 意味のある順序の達成基準」への対応について解説します。
Webアクセシビリティの基準は、見た目のデザインを整えること以上に、「情報を正しく伝える仕組み」を整えることが重要です。その中でも「意味のある順序」は、一見すると単純なようで、実務の中では意外と見落とされやすいポイントです。
本記事では、この達成基準の意味やよくある問題点、改善の方法、そして私たち制作会社が実際にどのように取り組んでいるかをご紹介します。
もくじ
「意味のある順序」とは?
視覚に依存しない情報伝達
「意味のある順序」とは、ページ上のコンテンツを 論理的に正しい順序で提供する ことを指します。
例えば、見出し・本文・リストの並びが視覚的には正しく見えても、裏側のHTML構造が崩れていると、スクリーンリーダーを利用している人には内容が正しく伝わりません。
- 正しい例:
<h2>→ 本文 → リスト → ボタン
- 誤った例:
- 本文の前にボタンが読み上げられる
- リストの途中で別の段落が割り込む
このように、見た目のデザインと実際の読み上げ順序が一致しているかが、達成基準1.3.2の本質です。
なぜ重要なのか
意味のある順序を守らなければ、利用者に誤解を与えたり、操作を誤らせる恐れがあります。
情報が正しく伝わらないというのは、ユーザー体験を大きく損なうだけでなく、Webサイト全体の信頼性にも影響します。
アクセシビリティに配慮したWeb制作は、単に法律や基準に従うためではなく、利用者に誠実に情報を届けるための姿勢と言えます。
よくある問題と改善例
CSSによる視覚的な並び替え
最近のWeb制作では、CSSのflexやgridを用いて、画面上の並びを自由に変更することができます。
しかし、HTML上の順序を無視して配置してしまうと、スクリーンリーダーはソースコードの順序通りに読み上げるため、意味が崩れてしまうのです。
- 【問題例】
- HTMLでは「本文→ボタン→見出し」だが、CSSで「見出し→本文→ボタン」と並べ替え
- 【改善策】
- HTML自体を論理的な順序で記述し、その上でCSSで見た目を整える
表組みの誤用
表はデータを整理するのに便利ですが、デザイン目的で「レイアウト表」として使うと順序が乱れがちです。
スクリーンリーダーはセルを行や列ごとに読み上げるため、本来の意味と違う順序で伝わってしまうことがあります。
- 【改善策】
- レイアウトにはCSSを使用する
- 表は「データを整理するためだけに」使う
見出し構造の乱れ
見出しを「大きな文字に見せたいから」といって<div>や<span>にスタイルを付けてしまうケースがあります。これも意味のある順序を壊す代表例です。
- 【改善策】
- 論理構造を守り、見出しには
<h1>〜<h6>を使用する - デザインはCSSで調整する
- 論理構造を守り、見出しには
実務でのチェックポイント
ソースコードの読み上げ順序を意識する
画面に表示される見た目ではなく、コード上の順序を確認する習慣を持ちましょう。
開発段階でスクリーンリーダーを使ってみると、実際の読み上げ体験が確認できます。
デザインとアクセシビリティの両立
「見やすさ」と「読みやすさ」は必ずしも一致しません。
Webデザインでは「直感的に分かりやすい並び」を意識しますが、アクセシビリティの観点では「論理的に分かりやすい順序」が求められます。この2つをどう両立させるかが、制作会社の腕の見せどころです。
運用時の注意点
Webサイトは公開して終わりではありません。運用担当者が記事を追加するときにも、順序が崩れることがあります。
たとえば、WordPressのブロックエディターで「見出し」と「段落」を混在させたり、表を無理に使ったりすると、読み上げ順序が乱れやすくなります。
- 運用ルールをマニュアル化する
- 定期的にアクセシビリティチェックを行う
といった仕組みづくりが有効です。
意味のある順序がもたらす効果
公平な情報提供
公共性の高いWebサイトでは、誰が利用しても同じ情報を正しく受け取れることが求められます。意味のある順序を守ることで、公平性と信頼性を確保できます。
利便性の向上
正しい順序で構造化されていれば、スクリーンリーダーの利用者だけでなく、検索エンジンにとっても理解しやすいWebページになります。結果的にSEOの観点からも有利になるケースがあります。
将来の拡張性
論理的な構造を守って制作しておけば、後からデザインをリニューアルする際も柔軟に対応できます。逆に順序がバラバラなサイトは、改修時のコストが膨らむリスクがあります。
制作現場での取り組み
私たち道洋行では、単に見た目を整えるだけでなく、論理構造を重視したコーディング を基本としています。
具体的には、
- HTMLの構造を意識したコーディング
- デザインと読み上げ順序の両立
- 運用担当者へのマニュアル提供
といった取り組みを行っています。
「意味のある順序」というと細かい規則に思えますが、制作の段階から意識して設計すれば大きな負担にはなりません。逆に、後から修正する方が手間もコストもかかります。だからこそ、初期段階から正しく整えることが重要です。
まとめ
Webアクセシビリティ達成基準 1.3.2「意味のある順序」は、単なる形式的な基準ではなく、ユーザーに正しく情報を届けるための基本ルールです。
- コード上の順序を論理的に整える
- CSSで無理に順序を操作しない
- 運用段階でもルールを守る
これらを徹底することで、公平性・利便性・将来の拡張性を確保できます。
当社サービスに関するご相談・お見積もりなど、お気軽にお問い合わせください。


