Webアクセシビリティ達成基準「1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準」の話
- Webアクセシビリティ
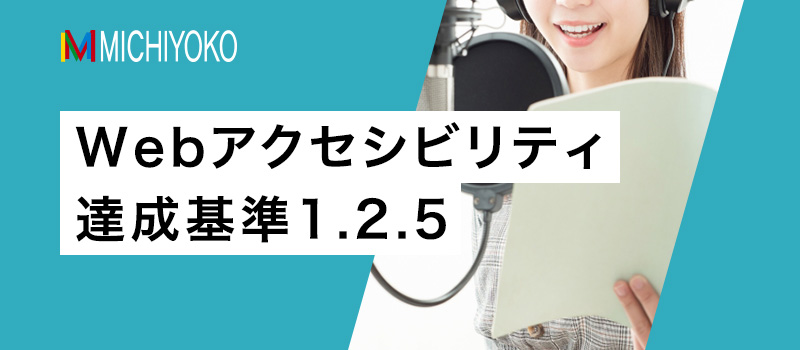
こんにちは、道洋行東京支店Web制作スタッフのT.Y.です。
前回はWebアクセシビリティ達成基準「1.2.4 キャプション(ライブ)」について解説しました。続けて今回は「1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準」への対応について解説します。
アクセシビリティの基準の中でも、見落とされがちな項目の一つが「音声解説」です。特に動画コンテンツを扱うページでは、情報が視覚に依存しがちなため、視覚障害のある方にとって大きなハードルとなります。
音声解説といえば、「1.2.3 音声解説、またはメディアに対する代替(収録済)」で解説しましたが、1.2.3が最低限の情報提供でよいのに対し、1.2.5では実際に「音声解説」が求められるため、ナレーションや解説トラックの追加が必要になります。
もくじ
「音声解説」とは?
Webアクセシビリティの達成基準「1.2.5 音声解説(収録済み)」とは、視覚的な情報を音声で説明することを指します。簡単に言えば、「映像だけでは伝わらない情報」をナレーションなどで補足する仕組みです。
たとえば以下のようなケースが該当します。
- 映像だけで伝えようとしている製品の使い方
- 表情や動きだけで表現されたメッセージ
- テキストやグラフが画面上に表示されるが、音声で読まれない
このような情報を視覚に頼らずに理解できるようにするのが「音声解説」の役割です。
収録済み音声解説の特徴
1.2.3は最低限の情報提供でよいですが、1.2.5では実際に「音声解説」が求められるため、映像の中に組み込まれたナレーションなどで、視覚情報を補足することが求められます。
なぜ1.2.5への対応が重要なのか?
視覚障害者にとっての「見えない」情報
視覚に障害のある方は、映像に頼ることができません。仮に字幕があったとしても、映像だけで伝わる内容(ジェスチャーや表情など)は把握できません。
音声解説は、こうした情報を誰もが公平に理解できるようにするための重要な手段です。
行政・公共機関の対応義務とトレンド
行政機関や自治体のWebサイトは、JIS X 8341-3:2016(WCAG 2.0準拠)に対応することが求められています。
このガイドラインには、「1.2.5」はレベルAAに位置づけられており、基本的に満たすべき基準とされています。
中小企業でも、自治体との取引や補助金関連の告知など、行政との接点がある場合は無視できません。
ESG・SDGsの観点からも評価される
企業の社会的責任(CSR)やSDGsの流れの中で、「誰一人取り残さない情報発信」は今や評価指標の一つです。
音声解説の導入は、ユニバーサルデザインへの配慮として企業価値の向上にもつながります。
音声解説(収録済み)の具体的な対応方法
どんな動画に必要か?
下記のような動画では、特に音声解説が必要とされるケースがあります。
- サービス紹介動画で、図や文字情報が映像でのみ提示されている
- 施設案内動画で、ナレーションなしに建物内部を撮影している
- 製品の操作手順を実演しているが、動作内容を音声で説明していない
対応の方法と選択肢
音声解説の対応にはいくつかの方法があります。
ナレーションを追加する
もっとも一般的なのは、動画編集時にナレーションを入れる方法です。
映像の中で視覚的に提示されている内容を、「この場面では○○が表示されています」といった形で視覚的な情報を音声で説明します。
音声ガイド付きの別バージョンを用意する
ひとつの動画にナレーションを加えるのが難しい場合、音声解説付きの別動画を用意する手法もあります。
「音声解説あり」動画と「通常版」を切り替えられるようにしておけば、利用者の選択肢も広がります。
音声解説の制作時のポイント
視覚情報の要点を明確にする
動画内で「何が視覚的に重要なのか」を明確にし、それを簡潔かつ的確な言葉で表現することが大切です。
例:
「右上に表示された赤いボタンをクリックしています」
「グラフは年々増加傾向を示しています」
「人物がうなずいて同意を示しています」
タイミングと聞きやすさの調整
ナレーションを入れるタイミングは映像の流れを妨げないように注意しましょう。
自然な間合いで、視聴者が理解しやすいリズムで説明することが大切です。
専門用語の説明も意識する
技術的な動画の場合は、専門用語の簡単な補足を入れるとより親切です。
特に行政や中小企業向けの製品紹介などでは、視聴者の専門知識の差を埋める工夫が効果的です。
まとめ:対応が差別化と信頼につながる
Webアクセシビリティの「1.2.5 音声解説(収録済み)」は、単なる義務ではなく、誰もが使えるWebサイトをつくる上での思いやりの基準です。
中小企業にとっては、「まだそこまで対応していない企業との差別化」に。
行政機関にとっては、「住民への公平な情報提供」の一環として。
そして私たち制作側にとっては、「信頼を得るための技術力の証明」に。
動画コンテンツが普及するいまこそ、視覚情報を補う「音声解説」の重要性はますます高まっています。
道洋行東京支店では、中小企業・行政機関向けにWebアクセシビリティ対応支援を手がけてきた実績があります。「まずは診断だけでもしてみたい」というご相談も歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
当社サービスに関するご相談・お見積もりなど、お気軽にお問い合わせください。


