Webアクセシビリティ達成基準「1.2.3 音声解説、またはメディアに対する代替(収録済)」の話
- Webアクセシビリティ
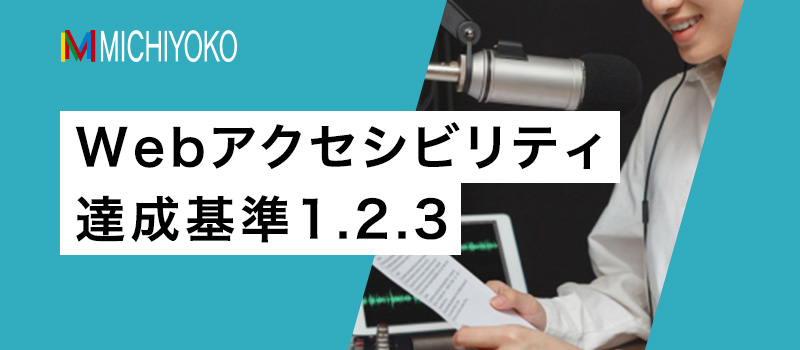
こんにちは、道洋行東京支店Web制作スタッフのT.Y.です。
前回はWebアクセシビリティ達成基準「1.2.2 キャプション(収録済み)」について解説しました。
続けて今回は「1.2.3 音声解説、またはメディアに対する代替(収録済)」への対応について解説します。
動画コンテンツの活用が進む中で、この基準に対応することは、情報の伝達力と信頼性の向上につながります。
現場での実装方法や注意点を、制作側の視点で具体的にまとめましたので、ぜひご参考ください。
もくじ
達成基準1.2.3の概要
求められる対応は2通り
この基準は、収録済みの映像コンテンツに対して、視覚的な情報を補足する手段を提供することを求めています。具体的な対応方法は以下のいずれかです。
- 音声解説
映像に含まれる視覚的な内容(登場人物の動作、環境、画面上のテキストなど)を、ナレーションの合間に音声で説明する形式。 - メディアに対する代替
動画コンテンツ全体の内容を文章で記述した、詳細なテキストコンテンツを別途提供する形式。
どちらか一方の提供で基準を満たすことができますが、実装のしやすさ、ユーザー層、サイトの目的に応じて適切な形式を選ぶことが重要です。
音声解説を取り入れる場合の実装ポイント
映像編集による追加
音声解説を導入する方法のひとつは、映像ファイルに直接解説音声を追加して編集し直す方法です。
ナレーションやセリフのない部分に音声解説を挿入し、ユーザーに違和感なく視覚情報を補足できるようにします。
ただし以下の点に注意が必要です。
- ナレーションの間に解説を入れるスペースがあるか
- 解説によって情報量が過多にならないか
- 音声合成ではなく、ナチュラルなナレーション音声で違和感を減らす工夫
別バージョンの動画を用意する場合
元の映像はそのままに、音声解説付きの別バージョンを用意し、ユーザーに選択肢を与える方法もあります。
このアプローチは以下のような利点があります。
- オリジナル映像に手を加えずに済む
- 必要なユーザーだけが音声解説付き映像を選べる
- サイト側の実装は比較的シンプル
ユーザーに配慮したインターフェース(例:音声解説付き動画へのリンクやボタンなど)を設置することで、体験を損なわずに対応が可能です。
メディアに対する代替テキストの提供
求められる情報の網羅性
「メディアに対する代替」は、動画に含まれるあらゆる情報を、文章で網羅的に記述することが求められます。
以下の内容をすべてカバーすることが理想です。
- 映像の進行や場面転換
- 重要な動きや視覚表現(ジェスチャー、表情など)
- 表示されるテキストや字幕
- ナレーションやセリフの内容
簡単なあらすじやスクリプトだけでは不十分です。視覚に頼らず、文章のみで映像の内容がイメージできるレベルの記述が必要です。
記述方法と配置の工夫
代替テキストはHTMLの中で以下のように設置できます。
<details>タグで折りたたみ式にする(冗長さを抑える)- 動画プレイヤーの直下に配置して、スクリーンリーダーの読み上げ順に配慮する
- CSSで読みやすさや文字サイズに配慮する
また、複数の動画がある場合は、動画ごとに対応した代替テキストを分けて記述しましょう。ユーザーが迷わずアクセスできる構造が重要です。
達成基準1.2.3対応の技術的留意点
字幕やキャプションとの混同に注意
音声解説と字幕(キャプション)は別物です。字幕は音声情報のテキスト化であり、視覚情報の補足にはなりません。
WCAGの1.2.3では「視覚的な要素の補足」が目的なので、字幕だけでは不十分という点を見落とさないようにしましょう。
対応レベルの整理(レベルA)
達成基準1.2.3は「レベルA」に該当します。これはWCAGの中で最も基本的な対応レベルであり、最低限対応すべき項目とされています。
この基準を満たしていない場合、JIS X 8341-3の「適合レベルA」にすら達しないという判断になるため、公共系サイトや補助金対象のWeb制作では特に重要です。
中小企業・行政担当者が取り組むべき理由
- 補助金・助成金での要件としてアクセシビリティ対応が求められるケースが増加中
- 高齢者や障がい者への配慮=企業の信頼性として評価されやすい
- ユーザー体験の向上・SEO強化にも直結
動画コンテンツを取り入れている企業や自治体のサイトでは、1.2.3への対応があるかどうかで、サイト全体の品質と信頼感が大きく左右されると言っても過言ではありません。
株式会社道洋行は、1979年創業の映像制作プロダクションとして、長年にわたりテレビ番組・CM・企業VP・Web動画・ポストプロダクション・MA(音声編集)・ENG取材・ブライダル撮影など、多彩な映像コンテンツの制作を手がけてきました。
本社のある石川県金沢市を拠点に、東京支店とも連携し、映像とWebの融合を強みに活動しています。
映像に対する代替テキストの作成や、収録済みメディアへの音声解説の追加、字幕やキャプションの最適化、HTML実装まで、映像とWebの両面から一貫してサポートできる体制が整っています。
動画とWebに精通した会社だからできる、現場目線のアクセシビリティ対応にぜひご期待ください。
当社サービスに関するご相談・お見積もりなど、お気軽にお問い合わせください。


