「ホームページ」という言葉の誤解
- コラム
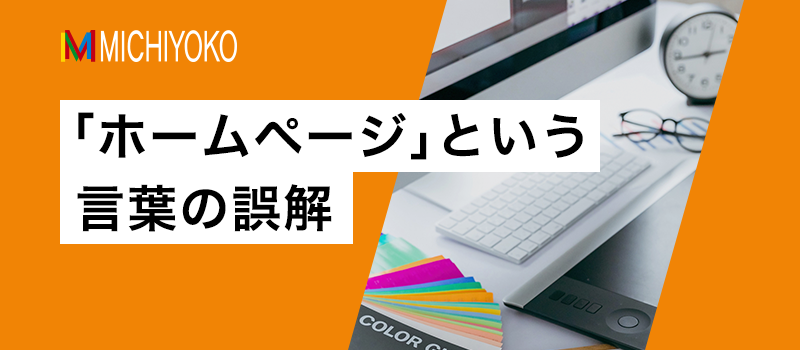
今回もちょっとした番外編。WEBの世界における「言葉」の話です。
「サーバー」を「サーバ」、「モニター」を「モニタ」と呼んだほうがかっこいいっぽい、とかではなく、意味の方についてです。
語義の誤解ネタとしては有名な話なので、知っている方も多いかもしれませんね。
Web制作の現場ではたびたび、「お客様との言葉のズレ」に直面します。
その例のひとつが、「ホームページ」という言葉です。
一見ごく普通の単語ですが、実は本来の意味と、日常会話での使われ方がまったく違うという、ちょっとしたズレがあるのです。
本来の「ホームページ」とは?
具体的に言うと、ホームページとは「ブラウザを起動したときに最初に表示されるページ」のことを指します。
つまり「Yahoo!をホームページに設定してる」などの言い方が、本来の意味に一番近い使い方です。
大抵の人は、自分がよくニュースをチェックするページであるとか、会社のパソコンではブラウザを経由して使うソフトウェアの起動画面がホームページになっている方もいるでしょう。
最近はタブブラウザの存在が当たり前になりましたので、何も表示されていないブランクのページをホームページとしている方も多いかもしれません。
日本での「ホームページ」の意味
ところが日本では、「ホームページ=Webサイト全体」のこととして使われることが非常に多くなっています。
たとえばこんな会話、聞いたことがあるかもしれません。
「うちのホームページ、そろそろリニューアルしたいんです」
こういう言い方をされた方が、「ブラウザを起動した時に最初に表示されるページをリニューアルしたい!」なんて意図をもって言われることは、まずありませんよね。
WEB制作会社の人間に限らず、そんなことを相談されても…となるでしょう。
ここでの言葉の意図は、当然「うちの所持しているWebサイトをリニューアルしたい」です。
会社のコーポレートサイトなのか、何かしらのメディア系ポータルサイトなのか、個人サイトなのかは別として、指すところは「Webサイト」ですね。
なぜズレが生まれたのか?
1990年代、日本にインターネットが本格的に普及し始めた頃、個人サイトや企業サイトを指して「ホームページ」と呼ぶ文化が根付きました。
特に初期のプロバイダ契約では、「あなた専用のホームページを開設できます」という案内が多く、この言葉が一気に広まったのです。
その結果、いまでも広い世代の方が、「ホームページ=会社のWebサイト」という感覚で使っています。
何が問題なのか?
何も問題ないんです。
何しろ、本当の意味での「ホームページ」について他人に相談するような場面なんて、まず滅多に存在しないのですから。
むしろ昔から「ホームページ」と「Webサイト」は同義語として扱われてきてしまったのですから、本来の意味を挙げて間違いを指摘する、なんて逆に無作法と言われそうですね。
(Web制作者にとっては、無関心でいてはいけないラインの言葉ではありますけど)
日本語の意味が時代を経るにつれて意味を変えていくことはよくありますが(二人称としての「貴様」がかつては目上相手に使う言葉であったりとか)、パソコン周りの言葉にもそういう経緯を経た言葉が出てきたのは、パソコンが当たり前の存在になってからそれだけ時間が経過した証拠とも言えそうです。
例えば若い世代の方は、携帯電話の通信においての「パケット使用量」の意味で「ギガ」という言葉を使ったりもしますね。
あれも正しい言葉の意味とは全く無縁な使い方ですが、今ではテレビCMでもフレーズとして使われるほど当たり前の用法になってきました。
でも正しく理解しているとかっこいい
「ホームページ」という言葉には、技術の歴史と文化の浸透が入り混じった誤解が詰まっています。
でもそのズレも、Webが社会に広く溶け込んだ証とも言えるのではないでしょうか。
もし貴方がWeb制作会社へ仕事を依頼する立場だった場合、「ホームページ」と言ってしまいそうな場面で「Webサイト」と言葉を正しく使い分けていれば、『この人はわかっている人だな!』と思われるかもしれませんよ。
当社サービスに関するご相談・お見積もりなど、お気軽にお問い合わせください。


